




1年生が、木津川市老人クラブの村井さんからいただいた竹トンボで昔遊びを楽しみました。初めは、なかなか飛ばし方がわからず苦戦していましたが…。回転させ方が分かってくると、空へ高く舞い上がるようになっていき、大はしゃぎでした。コツをつかむまでが難しいですが、コツがつかめるとどんどん飛ぶようになりますね。氷作りも大成功でした。

6年生が1年間積み上げてきたことに対して、在校生からどんなプレゼントがもらえるのかが、楽しみな6年生を送る会(6年生にとっては、『送られる会』)。今の自分たちをふり返った時、あこがれられる6年生になれていますか?ヒーローになれていますか?まだ高められるところがありますか?当日に味わえる感情は、自分たちが頑張ってきた分だけ、自分たちに返ってきます。伝えるべき加茂小学校の伝統は伝えきれていますか?
6年生も、在校生も大きく成長を遂げる3学期ですが、1月が終わりました。次は、6年生を送る会。楽しみで仕方がありません。
フライング…競争などで、スタートの号砲に先立って飛び出すこと。不正出発。
『ナイスフライング!?』
今日から「家庭学習P-up週間」が始まりますが、それに先立って「自主勉強」をできた人がいました。時間の記録にプラスすることはできないのに…素敵です。勉強に、フライングはありません。自分が伸びるために先に始めることは素敵なことです。中身も、先回り(予習)が許されています。もちろん逆走(復習)もありです。「賢くなる」というゴールが同じなら、自分にとって必要な道が見えてきます。
1年生国語科「たぬきの糸車」では、自分の気に入った場面について、工夫をしながら音読を楽しみました。
セリフや場面によって、ゆっくり読んだり、声の大きさや間を変えて読んでみたり、個性が出ていた発表会。子ども達は、声が出すのが苦手な子のがんばりに耳を澄ませて聞いたり、得意な子の読み方に驚かせられたりたくさんの発見のある時間となっていました。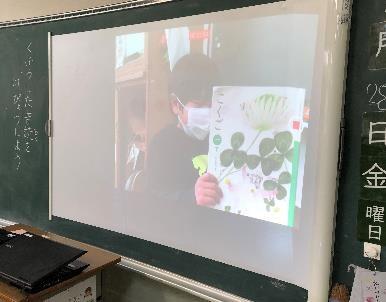


苦手の漢字を覚えようと繰り返しノートに練習する姿。はみ出して一回多く書いています。まさに一人切磋琢磨です。
「私の方がきれいに書いてるやろ?」「ぼくの方がきれいやって!」「本当やきれいに書いてるやん」「そっちもね」お互いがきれいな字を目指し、得点につながる。これも共に切磋琢磨です。今年度ラストの家庭学習P-up週間が月曜日から始まります。4月と比べて、家庭学習への取り組み方は違っていますか。パワーアップできたことはなんですか。
お家の人にも先生にもパワーアップした姿を見せてくださいね。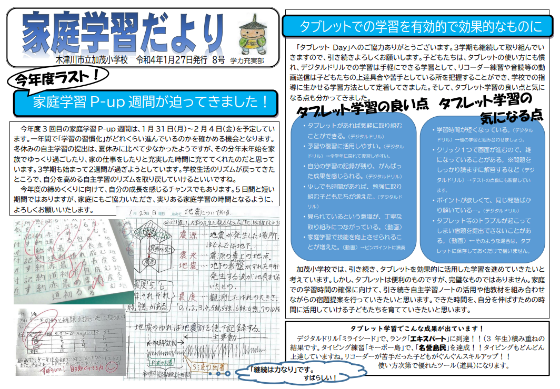 左側にPDFがあります。
左側にPDFがあります。物事を吸収するには、上達するには自分のコップがどちらを向いているかが大切です。上向きのコップには飲み物を注ぐことができ、溜まっていきます。それと同じように、自分がやってみよう、がんばってみようしている人は、アドバイスを受け入れることができたり、失敗も受け入れたりできます。そうすると、力となって身に付いていきます。
しかし、コップが下向きになっている状態(聞く耳が持てない・嫌々やっている)だと、なかなか身に付かず、成長に気付きにくくなってしまいます。下向きのコップに飲み物を注ぐことはできません。それと同じです。 少しでも上を向けば注ぐことはができます。
少しでも上を向けば注ぐことはができます。
5年生が、理科「ものの溶け方」の授業で実験をしていました。ものがとけることにはどんなきまりがあるのか、生活を振り返ったり、知っている知識を総動員したりして、予想を立てていきます。
「絶対そうなるって!」「そうなると思う!」は果たして本当なのか、こればっかりは、目の前で実験して確かめるしかありません。目の前の現象を観察して考察して、初めて「わかる」になります。もしかしたら、知っているその知識は間違っている・フェイク(偽物)かもしれません。
そして、知っている答えと一致しない時も、実験の楽しさです。「そうなるはずなのに…なぜ?」これが解明できると博士に近づきますね。
ICTサポーターさんにご協力いただき、全校でプログラミング教育を進めています。タブレットを使って学習するものもあれば、鉛筆と紙を使ってプログラミングの考え方を学習するもの、教科と関連させて学習するものなど様々です。



令和7年度 次回授業参観の日程
2月20日【金】
<授 業 参 観>
13:30 ~ 14:15
<学級懇談会>
14:30 ~ 15:00
ブックマーケットも同時開催いたします。
ご参加よろしくお願いいたします。
『学習の習慣化』を目指していきましょう。
家庭学習アドバイスシート.pdf
加茂小自主学習(児童用).pdf
かもっ子の自主学習を紹介しています。
ぜひご覧ください。
子ども110番の家・安全マップ