



















 ごはん 厚揚げと豚肉の味噌炒め けんちん汁 牛乳
ごはん 厚揚げと豚肉の味噌炒め けんちん汁 牛乳


 ごはん 鶏肉のさっぱり煮 キャベツのおかか和え 牛乳
ごはん 鶏肉のさっぱり煮 キャベツのおかか和え 牛乳 
 ごはん 賀茂なす(なす)の肉味噌あんかけ 具だくさんすまし汁 牛乳
ごはん 賀茂なす(なす)の肉味噌あんかけ 具だくさんすまし汁 牛乳 
 黒糖パン チキンとポテトのケチャップ炒め コーンクリームスープ 牛乳
黒糖パン チキンとポテトのケチャップ炒め コーンクリームスープ 牛乳 


 チャーハン 鶏の唐揚げ チンゲンサイのスープ 牛乳
チャーハン 鶏の唐揚げ チンゲンサイのスープ 牛乳 

 ごはん ハッシュドビーフ さっぱりサラダ 牛乳
ごはん ハッシュドビーフ さっぱりサラダ 牛乳 




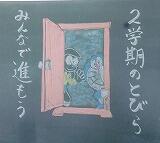
 ひまわりも、暑さでうなだれています。
ひまわりも、暑さでうなだれています。 写真の中に、4匹のクマゼミがいます。鳴き声が暑さを倍増させています。
写真の中に、4匹のクマゼミがいます。鳴き声が暑さを倍増させています。 セミの抜け殻もたくさん。この中に4つの抜け殻があります。
セミの抜け殻もたくさん。この中に4つの抜け殻があります。 観察池のメダカの学校
観察池のメダカの学校


気象警報発令時の登下校
震度5弱以上の地震が発生した場合の対応について
下記の文書をご確認ください。
R7地震対応について(保護者文書).pdf
ログインは右上のログインからお入りください





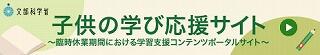

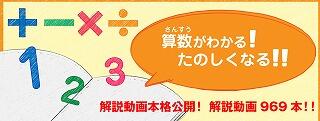

携帯・スマートフォンからもご覧いただけます。
以下のQRコードをご利用ください。